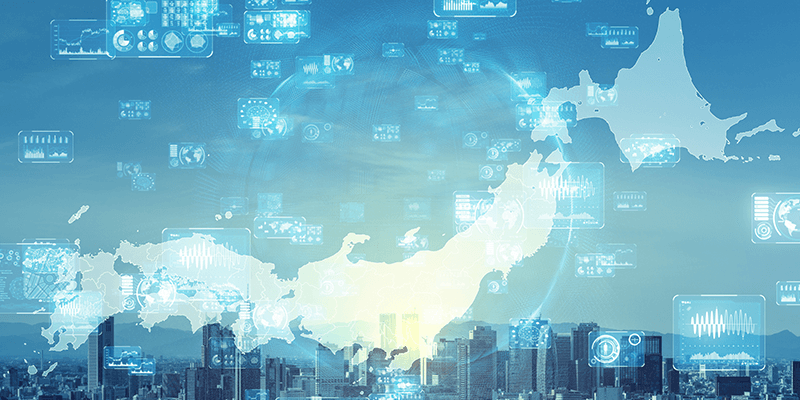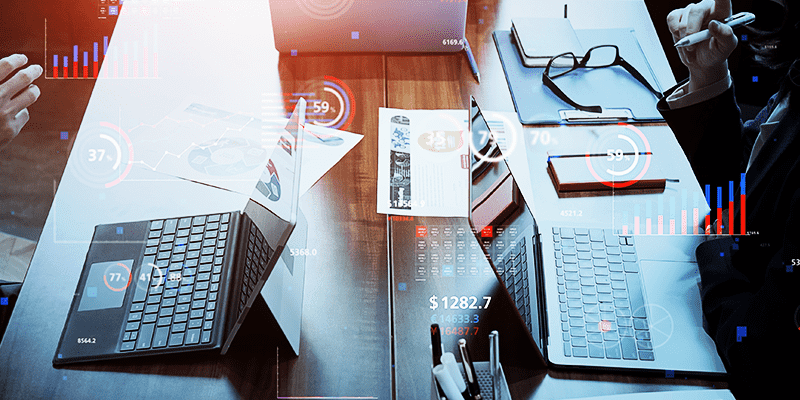BtoBマーケティングにおける戦略の考え方と成功事例

近年、BtoB企業でもデジタルマーケティングに取り組むのが当たり前になりつつあります。
ただし、「購買行動プロセスが複雑」、「意思決定関与者が多い」などのBtoCとは異なる点が多いため、それらを押さえたマーケティング戦略を立てなければ、継続的な成果を生み出すことは難しいでしょう。
本記事では、BtoCとBtoBのマーケティングにおける違いや、BtoBマーケティング戦略の考え方を解説し、フレームワークや成功事例を通じて、実践的な知識を提供します。
BtoBマーケティングの現状
BtoB企業のマーケティング担当者500名への「デジタルマーケティングをいつから実施していますか?」というアンケート調査では、コロナ前は約40%程度だったものの、コロナ禍以降の2020年~2022年にかけては約80%のユーザーが実施、2023年に新たにデジタルマーケティングを始めた企業はわずか6.6%に留まりました。(当社調べ)

また、年間のデジタルマーケティング予算は「100万円~1,000万円未満」が40.7%と多くなっていますが、「1,000万円~5,000万円未満」で23.6%、「5,000万円~1億円未満」で6.9%、「1億円以上」は12.6%となっており、多額の費用をかけてデジタルマーケティングを実施している企業も多く、各社のデジタルマーケティングへの期待が見受けられます。

この様に今やデジタルマーケティングはBtoB、BtoC問わず、各社において一般的な取り組みになっていると言えるでしょう。
BtoBデジタルマーケティング実態調査 ダウンロードはこちら
しかし、BtoB企業がデジタルマーケティングを行う場合は、BtoCとの違いを理解した上で進めなければ、期待する効果が得づらいという事実も有ります。
以下で、その違いについて詳しくご説明いたします。
BtoCとBtoBの違い
BtoCとBtoBマーケティングの違いを理解するにあたり、BtoBの購買行動の4つの特徴を見てみましょう。
①見込み客は「信頼性」「確実性」を重視する
BtoBの購買行動活動においては、取引企業選定の失敗は担当者1人の責任ではおさまらず、かつ、その失敗は選定担当者自身の評価にも関わってきます。
そのため、BtoBの購買行動においては、商品の「信頼性」「確実性」を重視した購買行動が行われる傾向が強くなります。
商品の魅力を中心に訴求するBtoCとは異なり、BtoBマーケティングでは商品だけでなく、企業の信頼性訴求策が成果に影響を与えます。
②見込客は社内説明を必要とする
決裁者が1人で決めるといった場合を除き、通常はBtoBの購買行動は、商品選定を担当者が一人で進めることは少なく、上司や同僚・関係部署に報告・相談をしながら進めていきます。
そのため、社内説明がしにくい商品、つまり訴求点が不明確な商品は検討対象から外れていきます。
BtoBマーケティングでは、企業選定担当者が「この商品はこんな強みがある商品だから我が社に向いています」とできる限り端的に社内関係者に説明が出来るよう、商品の印象付けやメッセージの伝達を行う必要があります。
③見込み客は「感覚」ではなく「論理」で判断する
BtoCと異なり、BtoB取引には結果が求められます。
商品を購入して、どのような効果・成果が得られたか、報告が求められます。
また、②に記載の通り、複数の関係者への説明が求められることも影響し、「感覚」による購買行動は行われにくく、「論理」による購買行動が行われます。
見込客は「自社の課題解決・ニーズ充足ができる商品はどれだろうか」「費用対効果が高い商品はどれだろうか」「他社とどの様な違いがあるだろうか」という観点に立ち、論理的に比較検討を行っています。
②と関連しますが、「感覚」に訴えるBtoCとは異なり、「なぜ自社商品が最適なのか」を明確に発信できるかどうかがBtoBマーケティングの成果に大きく影響します。
④営業活動まで視野に入れた取り組みが求められる
営業活動を必要としないSaaSプロダクトなど、一部の例外を除き、BtoBマーケティングは、「商談の創出」が目的になります。
ただ数を増やすことを志向するのではなく、より「受注につながりやすい商談を創出していくこと」がBtoBマーケティングの役割です。
そのため、BtoBマーケティングには、案件発掘に留まらず、営業効率化のための情報収集までその範囲に含みます。
「問い合わせをしてきた企業が有望見込み客なのかどうか、どんなニーズがありそうか」「営業中顧客の内、前向きに検討してくれているのはどの企業なのか」「過去営業先・過去取引先企業で、案件が発生しそうなところは無いか」などの情報のフィードバックまで含めたマーケティング設計を考えることで、大きな成果を生み出すことが可能になります。
BtoBマーケティング戦略策定の前に知っておくべき戦略・戦術・戦闘の違い
BtoBマーケティングにおいて戦略策定は成功を左右する重要なプロセスです。しかし、多くの企業が戦略、戦術、戦闘の違いを理解せずに取り組んでしまい、結果的に効果を上げられないことが少なくありません。まずはこれらの違いを明確に理解することが、効果的なBtoBマーケティングに繋がります。
戦略とは
戦略とは、他社に対して優位性を築くための資源配分のパターンと弊社では捉えています。全ての箇所に資源を充分に配分することは不可能なため、有限である資源を成果が出る部分にどれだけ配分するかが重要になってきます。
以下は、保有資源が100のA社とB社、そして保有資源が250あるC社における資源配分を比較したものです。

B社は、25の領域に均等に資源を配分したことで、1つの領域では4の資源配分となってしまい、保有資源250で均等配分をしているC社に資源配分で負けてしまっています。
対して、B社と同じ保有資源を持っているA社は資源を集中させる領域を決めているため、ある特定領域においてはC社を上回る資源投入に成功し、成果が出やすい環境を創り出しています。
この様に、「どの領域に重点的に資源配分を行い、他社を圧倒する競争力を身に着けていくのか」を決めることが「戦略」です。そして、「戦略」を決める際、以下3つの組み合わせで最も競争優位性を発揮できる組み合わせを見つけることが重要となります。
- ① ポジショニングとエビデンス
- ② ターゲットとニーズ
- ③ 自社の強みと競争優位性
① ポジショニングとエビデンス
見込客は多くの場合ワンメッセージしか記憶しないと言われており、購入判断もそのワンメッセージに基づいて行われます。たとえ商品・サービスについて細部まで比較検討したとしても、最終的な決定は見込客の心に残るワンメッセージに基づいて、自社に最も適したものを選ぶというのが実際の購買行動なのです。
しかし、たとえワンメッセージが適切であったとしても、それを直接的に伝えるだけでは見込客の記憶には残りません。見込客が自分自身で考えた結果として導き出されたメッセージのみが心に刻まれます。そのため、理想的なマーケティング活動を行うためには、次のような流れを作る必要があります。
- 1. メッセージを裏付けるエビデンスを豊富に提示する。
- 2. 見込客がエビデンスを確認する過程で、こちらが意図したワンメッセージにたどり着くように導く。
- 3. 見込客が自分で発見した(と思う)メッセージを基に、社内での説明や説得を進めてもらう。
- 4. そのメッセージが競争優位性を持つものであること。
このようなプロセスを経て、ワンメッセージを見込客の心に残していきます。
② ターゲットとニーズ
効果的なメッセージは、ターゲットごとに異なるため、ターゲットの選定は、ワンメッセージの策定と同時進行で行われます。つまり、ワンメッセージは理想を言えばターゲットごとにつくり、ターゲットごとに伝えることが求められています。
ターゲットの定義には、以下の様な様々な要素がありますが、これらは組み合わせる場合もありますし、単一の設定の場合もあります。
- 企業規模
- 部署
- 役職
- 年代
- ニーズ
- 購買行動プロセス
ただ、いずれにしてもニーズと購買行動プロセスは必ず考えるべき項目と当社では考えています。なぜならば、ニーズが分からなければターゲットに刺さるワンメッセージは作れませんし、購買行動が分からなければ、最適なタッチポイント設計が出来ないためです。
③ 自社の強みと競争優位性
ワンメッセージを尖らせるためには、競合企業と商品・サービス、企業の強みを比較し、何が競争優位になりうるのか考えることが重要です。
マーケティングの勝負は頭の中で行われますが、取引が発生した際に、ワンメッセージと商品・サービスの強みに乖離があれば、クレームや不満を生み出してしまいかねません。そのため、ワンメッセージは競争優位性に立脚し、「比較検討先のA社よりもこの点で圧倒的に優れている」と見込客に認識してもらうことがリスク回避としても重要です。
戦術とは
戦術とは、戦略を効果的に実現するためのシナリオを検討することを指します。例えばSEOであれば、どの様なキーワードで、どのページに見込客を集客し、そのページでどの様なメッセージを発信し、どんなアクションを起こしてもらうのか考えます。これをSEOだけでなく、広告、MAなど、実施するすべての施策についてシナリオを検討し、どの様に統合していくかを検討するのが戦術になります。
カスタマージャーニーに基づき、各ターゲットに対して最適なメッセージを伝えるインフラの整備や、最適な予算配分を行うことが重要です。戦術が適切であることで、戦略の実現性が高まり、効果的なマーケティング活動が可能となります。
戦闘とは
戦闘とは、SEOや広告、Webサイト改善など、具体的な施策そのものを指します。戦略、戦術で確定した方針を各々の施策で実行していくフェーズです。
戦闘レベルの改善により、見込客の心情や雰囲気を盛り上げることで購買に至るBtoCと異なり、BtoBにおいては、購入にあたって組織単位で冷静な比較検討を行うため、戦略や戦術での綿密な計画と施策が不可欠であり、戦略戦術の欠落は成果創出の大きな阻害要因になりえます。
戦略策定から取り組んだBtoBマーケティング成功事例
BtoBマーケティングでは、施策の実行だけではなく、戦略的なアプローチが成功の鍵を握ります。ここでは、戦略策定から取り組むことで大きな成果を上げたBtoB企業の成功事例を紹介します。
事例1:ピークが過ぎた商品にて戦略をゼロベースで見直し、成果創出
課題
クラウドツールの導入支援サービスを提供した企業の支援事例です。既にこの市場では新規導入企業は一巡し、市場自体が縮小していました。ピーク時には、広告露出を高めれば一定の反応が得られましたが、市場が縮小してしまった後は、様々なWeb施策を実行しても反応が得られず、検索広告やSEOを実施しても、そもそも検索母数が減ってしまっており、十分な集客が得られなくなっていました。
そこで、従来の「新規導入支援」中心の訴求を、「代理店乗り換え」「利用拡大」に切り替え、導入済み企業を対象としたマーケティングに切り替えることをご提案しました。
ご支援内容
- 1. デジタルマーケティング戦略の見直し
- 2. 情報サイトの構築
- 3. 周辺ニーズへのリーチ
- 4. 時流を意識したマーケティング企画
成果
検索ボリュームが月間10回程度で顕在ニーズがほとんどない商材ではありましたが、月間の新規問い合わせ発生数で毎月50件程度、リード獲得数で100件以上を達成しました。
事例2:新規事業立ち上げ。戦略策定~テストマーケティングまで実施し新規開拓モデル構築。
課題
立ち上げが難航することが多い新規市場×新商品の新規事業立ち上げで、どのようにターゲティングするか、どのようなメッセージを発信していくか、決めかねていました。また、従来のサービス提供分野とは性質が異なる分野であり、一定の精度を持った仮説を立てることも困難でした。そこで、当社からは、デジタルマーケティング戦略は最初の段階では絞り込みすぎず、いくつかの選択肢を残し、テストマーケティングでデータを収集しながら、戦略の絞り込みを行っていくことをご提案いたしました。
ご支援内容
- 1. デジタルマーケティング戦略の策定
- 2. テストマーケティングの実施
- 3. コンテンツマーケティング展開
- 4. 広告費を削減しSEO中心に
成果
新規事業は無事に立ち上がりました。SEO強化により、現在では、最小の広告費のみで一定のリード獲得数を維持しています。
事例3:デジタルマーケティング戦略の開発で新規受注の5割をデジタル経由に
課題
他事業の既存顧客営業や紹介営業など、人的営業を中心に事業展開を図っていたものの、なかなか受注獲得が進みませんでした。そこで完全新規客へのリーチを強化すべくデジタルマーケティングを開始。しかしながら、先行している競合企業が多数あり、デジタルマーケティングによる新規開拓に苦戦していました。そんな状況下で当社にお声がけいただき、「急がば回れ」でデジタルマーケティング戦略をゼロベースで見直すことになりました。
ご支援内容
- 1. デジタルとリアルを融合した顧客接点戦略を構築
- 2. 自社に有利なポジショニングを模索
- 3. ポジショニングを強化するためのコンテンツ拡充
- 4. 多数のゴールアクションを用意
成果
お客様と伴走しながら、試行錯誤を繰り返し、ご支援開始3年経過時点では、新規受注の5割(年間約5億円)がデジタルマーケティング経由での受注になりました。
BtoBマーケティングの流れ

BtoBマーケティングでの戦略立案にあたっては、全体像の理解が出来ていないと戦略を戦術に落とし込むことができません。そのため、戦略策定以降のBtoBマーケティングの流れをご説明いたします。
①リードジェネレーション
リードジェネレーション(lead generation)とは自社の商品・サービスに興味を持っている見込み顧客を獲得するためのマーケティング活動を指します。具体的にはメールアドレスや電話番号といった個人情報を獲得することが目的となります。
②リードナーチャリング
リードナーチャリング(lead nurturing)とは、獲得した見込み顧客を育成するためのマーケティング活動です。リード獲得したばかりの見込み顧客は購買意欲が高まっていないことが多いため、いきなり営業アプローチをかけても成約には至りにくいです。そのため、メルマガ配信などで定期的に接点を維持、購買タイミングが来たときに指名で問い合わせてもらう取組みが必要です。
③リードクオリフィケーション
リードクオリフィケーション(lead qualification)とは、確度の高い見込み顧客を絞り込むことです。リードの中には、商材に興味はあるもののまだ商材の選定フェーズまで至っていないリードや、社内での起案が通らなかったリードもあるため、その時まさに比較検討していて営業アプローチをすべきリードを選定する必要があるのです。一般的にはMA(マーケティングオートメーション)やSFA(セールスフォースオートメーション)でリードごとにスコアリングを行うことで、確度の高いリードをホットリードとして見極めていきます。
④営業
アプローチすべきリードが選定出来たタイミングで、営業がアプローチしていきます。リード数が少ない場合は営業が直接アプローチすることが多いですが、リード数が多くなると営業リソースを割くことも難しくなります。そのような場合、インサイドセールスとフィールドセールスに分業し、リードのファーストコンタクトをインサイドセールスが行い、アポイントが獲得できたリードをフィールドセールスにパスする形で営業の効率化を図る場合もあります。
⑤顧客維持
BtoBマーケティングでは、顧客維持も欠かせない取り組みの一つです。契約後の顧客との関係を維持することで、クロスセル・アップセルに繋げLTVを最大化することができます。
以上のようにBtoBマーケティングには流れがあり、取り組み段階によって必要な施策は異なります。ホワイトペーパーやメールマーケティングという多くの企業が既に行っている施策でも、全体像を理解して戦略を立てて取り組むことが、BtoBマーケティングの効果を最大化するためには必要不可欠と言えます。
その他:BtoBマーケティングの戦略策定時に使われるフレームワーク
最後に、BtoC、BtoB問わずマーケティング戦略を策定するにあたり、一般的に使われるフレームワークをご紹介したいと思います。
PEST分析
PEST分析は、政治(Political)、経済(Economic)、社会(Social)、技術(Technological)の4つの外部環境要因を分析する手法です。この分析により、企業は外部環境の変化を予測し、戦略に反映させることができます。例えば、新しい技術の登場や規制の変更は、企業の戦略に大きな影響を与える可能性があるため、PEST分析を用いて分析します。
5F分析
5F分析は、マイケル・ポーターが提唱した競争要因分析のフレームワークで、業界の競争構造を理解するために用いられます。具体的には、新規参入者の脅威、供給者の交渉力、買い手の交渉力、代替品の脅威、既存競争企業間の競争の5つの要因を評価します。これにより競争環境を把握し、競争優位性を築くための戦略を策定します。
3C分析
3C分析は、顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3つの視点から市場を分析するフレームワークです。BtoB企業は、顧客のニーズや競合の動向を理解し、自社の強みを活かした戦略を立案します。この分析により、ターゲット市場を明確にし、競争優位を維持するための施策を検討することが可能です。
STP分析
STP分析は、セグメンテーション(Segmentation)、ターゲティング(Targeting)、ポジショニング(Positioning)の3つのプロセスを通じて市場を分析する手法です。ターゲット市場をセグメント化し、最適なターゲットを選定、その市場における自社のポジショニングを明確化します。これにより、顧客に対する明確な価値提案を行うことなどに役立ちます。
4P分析
4P分析は、製品(Product)、価格(Price)、場所(Place)、プロモーション(Promotion)の4つの要素からマーケティング戦略を策定するフレームワークです。これらの要素を組み合わせて、ターゲット顧客に対する最適なマーケティングミックスを構築します。
6R
6Rは、リーチ(Reach)、リレーション(Relation)、リサーチ(Research)、リターン(Return)、レピュテーション(Reputation)、リテンション(Retention)の6つの要素を考慮したマーケティング戦略のフレームワークです。この評価基準を用いて、マーケティング活動の効果を測定し、改善策を導き出すこと等に使用します。
まとめ
いかがでしたか。本記事では、BtoBマーケティングにおける戦略の考え方や戦略策定に役立つフレームワーク、成功事例などをご紹介しました。BtoBマーケティングでは、BtoCと異なる点や業界・商材の特性を理解し、施策に頼るのではなく、しっかりとした戦略を立てることが重要です。業界や商材の特性、ターゲットのリテラシーを深く理解し、それに基づいた情報提供とコミュニケーション戦略を策定することが求められます。そのため、BtoBマーケティングで成功を目指す企業は、まず戦略の策定に取り組むことをおすすめします。
リーディング・ソリューションでは、BtoBデジタルマーケティングにおいて20年以上の歴史があり、様々な業界、商材の支援実績があります。BtoBならではのマーケティング戦略策定から実行までを一貫してサポートし、貴社のビジネス成長を支援します。詳細は以下よりご覧ください。